アートトーク・コーチング・ファシリテーター®(ATCF)とは、当協会の「対話型鑑賞ファシリテーター養成講座」プログラムを受講して認定された「プロフェッショナル講師」を指します。
アートトーク・コーチング・ファシリテーター®(ATCF)が実現できる3つのこと
- アイデア能力UP
- アートトークで組織のマネジメント
- 正解のない課題(問い)に挑む力の育成
「対話型鑑賞ファシリテーター養成講座」とは、美術作品などのアートを介して、参加者同士の対話による深い学びやコミュニケーションを促進する専門家「ファシリテーター」を育成するための講座です。
「対話型鑑賞ファシリテーター」の源流について
この活動の源流は、アメリカで起こった教育改革にあります。
その意義を完全に理解するためには、アメリカでの歴史と広がりに遡ることが不可欠です。
アメリカでの歴史と広がりは「美術鑑賞への科学的アプローチ」
今日の対話型鑑賞プログラムは、1980年代にアメリカの美術教育で起こった大きな転換にそのルーツを持ちます。この変化は、従来の講義形式の教育法への批判的な再評価から生まれ、科学的な研究に基づいた土台の上に築かれました。
このムーブメントの知的支柱となったのが、ハーバード大学の認知心理学者であったアビゲイル・ハウゼン博士の研究です。
なぜ多くの人々が美術館で居心地の悪さを感じるのかという疑問を抱いたハウゼン氏は、長年の研究と数千人へのインタビューを通じて、人々がアート作品に意味を見出す能力を発達させる過程には、予測可能なパターン、すなわち「段階」があることを発見しました。
彼女の「美的発達段階(Stages of Aesthetic Development)」理論は、鑑賞者が5つの段階を経て、単純な物語的な理解(段階I:物語的)から、より複雑で内省的な解釈(段階V:再創造的)へと進んでいくことを示しました。
ハウゼン氏の画期的な研究は、専門家による解釈や事実を教えることに重きを置いた従来の美術教育が、鑑賞者を初期段階から先に進ませる手助けになっていないことが多いという事実を明らかにしました。
鑑賞者は、自分で「見る方法」を教わるのではなく、「何を見るべきか」を一方的に伝えられていたのです。(過去)
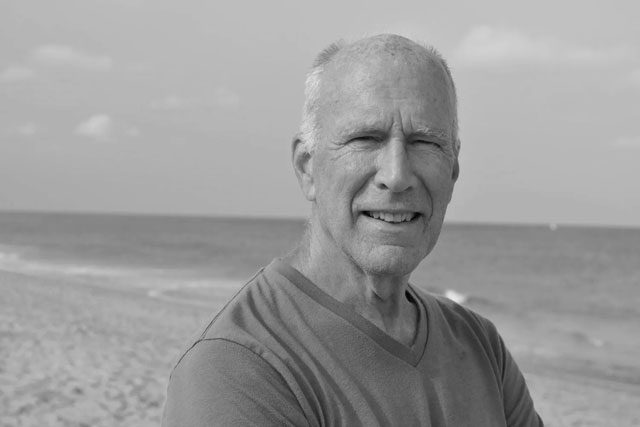
ここで登場するのが、当時MoMAの教育部長であったフィリップ・ヤノウィン氏です。既存の教育プログラムの効果に限界を感じていた彼は、ハウゼン氏の研究に出会います。二人は彼女の研究結果に直接基づいた教育法を共同で開発しました。
この方法は、事実を教えるのではなく、鑑賞者自身が思考スキルを伸ばし、美的発達の段階を自然に上がっていくのを手助けするために設計されました。
この協働からVTS(Visual Thinking Strategies)が誕生したのです。
VTSは、「作品の解釈に唯一の正解はない」という考えに基づき、鑑賞者がアートをじっくりと「見る(観察)」ことから始め、そこから「考えた(思考)こと」を「言葉(話す、伝達する)」にし、他者の意見を「聞く(傾聴)」という4つのプロセスを重視します。
今では有名になったVTSの3つの質問は、ハウゼン氏の理論を実践に落とし込むためのツールとして、細心の注意を払って設計されました。
What’s going on in this picture? (この絵では何が起きていますか?)
→あらゆる段階の鑑賞者に、観察と最初の思考を促す。
What do you see that makes you say that? (そう思うのは、作品のどこからですか?)
→根拠に基づいた思考を促進する。
What more can we find? (ほかに何が見つかりますか?)
→より深く、徹底した観察と協働的な発見を促す。
MoMAでの成功の後、VTSは急速に広がりました。
1995年、ハウゼン氏とヤノウィン氏は、カリキュラムと教員研修を広く提供するために、NPO法人「Visual Understanding in Education (VUE)」(現在のVTS組織の前身)を共同で設立しました。
VTSは、特にアメリカ全土のK-12(幼稚園から高校まで)の学区で熱心に採用されました。その魅力は、VTSがアートへの理解を深めるだけでなく、批判的思考力、ビジュアル・リテラシー、コミュニケーション能力、さらにはライティング能力といった、あらゆる学問分野で応用可能なスキルに測定可能な向上をもたらすことが研究で示された点にありました。
今日、VTSの応用は美術館や教室の枠をはるかに超えています。
医学教育
ハーバード大学医学部をはじめとする30以上の米国のメディカルスクールが、将来の医師の観察力と診断能力を向上させ、患者の微細な視覚的兆候に気づく手助けとしてVTSを用いています。
ビジネス
企業では、従業員のチームワーク、コミュニケーション、創造的な問題解決能力を高めるためにVTSが活用されています。
「クリティカルシンキング」と「ビジュアルシンキング」の違い
クリティカルシンキングとビジュアルシンキングは、どちらも複雑な問題を解決し、思考を深めるための強力なツールですが、その目的とアプローチが異なります。
簡単に言えば、以下のようになります。
クリティカルシンキング:物事を「深く掘り下げて真偽を問う」論理の思考法
ビジュアルシンキング:物事を「広く眺めて関係性を捉える」イメージの思考法
クリティカルシンキング(Critical Thinking)とは?
日本語で「批判的思考」と訳されますが、単に他者を批判するのではなく、「物事を無批判に受け入れず、客観的・論理的に分析し、本質を見極める」ための思考法です。
目的
情報の正しさや妥当性を評価する。
前提となっている事柄が本当に正しいかを疑う。
最適な意思決定や結論を導き出す。
プロセス
「なぜ?」「本当にそうか?」と問いを立てる。
事実と意見を切り分ける。
論理の矛盾や飛躍がないかを確認する。
多角的な視点から物事を検討する。
思考の方向性
主に「収束思考」。多くの情報や選択肢の中から、論理的な正しさや合理性に基づいて、最適な一つの答えへと絞り込んでいきます。
アウトプット
論理的な文章、評価、判断、説得力のある提案など。
ビジュアルシンキング(Visual Thinking)とは?
考えやアイデア、情報を図や絵、マインドマップなどの視覚的な要素を用いて整理し、思考を発展させる思考法です。頭の中にある漠然としたイメージを「見える化」します。
目的
複雑な情報を単純化し、全体像を把握する。
情報同士の関係性やパターンを発見する。
自由な発想を促し、新しいアイデアを生み出す。
プロセス
手で描く、書き出す(絵の上手さは問わない)。
要素を線でつないだり、グルーピングしたりする。
全体を俯瞰して、新たな気づきを得る。
思考の方向性
主に「拡散思考」。
一つのテーマから、関連する多くのアイデアや情報を自由に広げていきます。
アウトプット
マインドマップ、図解、コンセプトマップ、スケッチ、グラフィックレコードなど。
当協会が提案するのは「正解のない問いに応えられる人」の育成です。
先行きが不透明な現代では「正解のない問いに応えられる人」の存在が大きなカギになります。
そういった状況の中でロジカル(理論的)に物事を考えるだけでは、新しい発想、解決策等は生まれません。
自由な発想を促し、新しいアイデアを生み出す為にはビジュアルシンキングが最適なのです。
日本への導入と発展 福のり子氏の役割とACOP(京都芸術大学)設立
この確立され影響力を持つVTSという手法にコロンビア大学大学院を修了しニューヨーク近代美術館(MoMA)に勤務していた福のり子氏は出会いました。
その力を自ら体験した彼女は、VTSを日本に紹介するための熱心な提唱者となります。
その努力は、2004年の京都芸術大学におけるACOP(アート・コミュニケーション研究センター)の設立で結実しました。インディペンデント・キュレーターとしてニューヨークで活動後、京都芸術大学(旧:京都造形芸術大学)で教鞭をとったのが福のり子氏です。
ACOPは、現在もこれらの対話型の手法を日本の文脈に適応させ、広めるための中心的な拠点となり、その応用範囲を広げ、新たな分野での可能性を探求しています。
福氏は「こう見るべき」という一方的な解説ではなく、「自分が見えるままに見ればよい」と参加者に寄り添い、共に考える楽しさを伝えることの重要性を説きました。
そして、その活動の拠点となったのが、2004年に福氏が中心となって京都芸術大学に設立された「ACOP(アート・コミュニケーション研究センター)」です。
ACOPは、単にVTSの手法を導入するだけでなく、日本独自の文化的背景やコミュニケーションのあり方を踏まえ、より鑑賞を「深める」ことを追求しています。
そして当協会の理事長 江川のり子は、このACOPで学んでおります。
当協会の「対話型鑑賞ファシリテーター養成講座」プログラムの特徴
「対話型鑑賞ファシリテーター養成講座」では、MoMAのVTSを基礎理論として学びながら、福のり子氏が日本に根付かせ、ACOPのような先進的な機関が培ってきた実践的な知見に触れることができます。
さらに当協会がビジネスの分野においてACOPの実践的なビジュアルシンキングの基礎理論を活用して、当協会が開発したオリジナルのプログラムです。
体系的な学習プログラム
講座は複数部構成になっており、対話型鑑賞の基礎から、ファシリテーションの上級編、さらには「発想力」「チームビルディング」そのものを深く掘り下げる内容まで、段階的かつ体系的に学べるように設計されています。
実践重視の姿勢
講座内での実践演習に加え、定期的な練習会を設けるなど、ファシリテーションスキルを継続的に磨く機会を提供しています。
コミュニケーションの探求
「みる人と作品の間に立ち起こる不思議な現象」をアートと捉え、コミュニケーションという視点から人の変化や可能性を探求しています。
その活動は美術教育の枠を超え、近年ではビジネスや医学教育の分野でもとても注目されています。
理論と背景
- 福のり子氏が日本に紹介した、MoMA開発のVTSの思想と歴史
- 鑑賞者の観察力や思考力を引き出すための教育理論
- ACOPなどが探求する、コミュニケーションとしての鑑賞の可能性
ファシリテーションスキル
- VTSの3つの問いを核とした、効果的な問いかけの技術
- 参加者の発言を言い換え、要約し、対話を構造化する手法
- 福氏が重視し、ACOPが実践する、より深い対話を生むための場の醸成と介入のスキル
実践演習と応用
- 様々なアート作品を用いたファシリテーションの実践とフィードバック
- ビジネスパーソンにおける対象者に合わせたプログラムのデザイン
- ACOPの定期練習会のような、継続的な研鑽の場の活用
充実の教材
ACOPを背景にしたアカデミックな当協会オリジナルの教材を提供します。
認定後も分からないこと、再確認が容易にできる内容になっていますので「対話型鑑賞ファシリテーター」のご自身だけの「バイブル」としてご活用いただけます。
対話型鑑賞の主催者として必要なツールは、すべて協会から提供させて頂きますので初めての方も安心して「講師」業に専念頂くことができます。
また同じ志を持つ仲間を作ることで継続教育、レベルアップの機会が提供されます。
この講座は、アートの専門知識以上に、人の言葉に耳を傾け、思考を促し、新たな気づきの瞬間を共有することに喜びを感じる方に最適な学びの場です。福のり子氏という先駆者によって日本にもたらされ、豊かに育まれてきた対話型鑑賞の世界は、アートとの、そして他者との新しい関わり方を発見する旅へとあなたを誘ってくれるでしょう。

